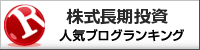「13年間で学んだこと」シリーズの4回目になります。
「13年間で学んだこと」シリーズの4回目になります。
●13年で学んだこと カテゴリーの記事一覧 - ユキマツの「長期投資のタイミング」
値上がりするものを買持ちするのが投資?
投資は基本的に
値上がりするものを見つけて買ってずっと持っておくもの
という一般通念、のようなものを感じるときがあります。
投資ってそういうもんでしょ、空売りなんて邪道、的な。
わたしは
必ずしもそうではない
と思います。
投資の一面:「価値」と「価格」間のズレの判断
わたしは投資には
●投資対象の「価値」と「価格」に
●どのようなズレをみるか
●その判断力を競い合うゲーム的な一面
もあると思います。
※こういう一面もあるのでは?という主張であり「投資は基本的に、値上がりするものを見つけてずっと持っておくもの」的なスタンスを否定するものではありません
3つの投資スタイル
例えば、ですが、
●投資対象の「価値」と「価格」に
●どのようなズレをみるか
●その判断力を競い合うゲーム
の例として3つ挙げてみます。
①ある投資対象の今の「価値」と20年後の「価値」を比べて、どの程度ズレがあるのか(同一銘柄での時間差での価値のズレ)を判断して行う投資
ある銘柄の今の価値が20年後に大幅に上がっていると判断するなら、現在の価格はあまり気にせずに買って長期保有するスタイルの投資。
投資タイミングを読まない長期的な株式インデックス投資などは長期的な価値の変化(ズレ)を期待する投資スタンスともいえる思います。
20年後、価値さえ十分に上がっていれば、いつ買ってもそこそこ価格はついてくるだろう、という判断、期待に根ざした投資スタンスともいえるかと。
②投資対象の現在の「価格」と「価値」にどの程度ずれがあるのか(同一銘柄での価値と価格のズレ)を判断して行う投資
ある銘柄の現在の
●価値に比べて価格が高すぎるなら割高⇒「売り」と判断。
●価値に比べて価格が低すぎるなら割安⇒「買い」と判断。
銘柄の現時点での「割安割高」の判断に基づいて行われる投資スタイルも存在すると思われます。
③複数の投資対象において、現在どちらがより割高か?(割安か?)(複数銘柄間の割高・割安度合いのズレ)を判断して行う投資
①②は同一銘柄における判断でしたが、同一ではなく複数の銘柄において
●より割高と判断される銘柄⇒売りポジション
●より割安と判断される銘柄⇒買いポジション
を作り、一定期間同時に保有し、割安割高が解消されればポジションを手じまう、という投資スタイル、も存在します。
例えば、何らかの理由でトヨタ株が割高、日産株が割安と判断されるなら、
●トヨタ株⇒売りポジション
●日産株⇒買いポジション
を作り、一定期間同時に保有し、割安割高が解消されることを期待する、ような投資スタイルです。
③のようなスタイルはロングショート(戦略)の一つの形であり、わたしは2014年から試行、2015年後半から本格的に実施しています。
ロングショートのいいところ
例として挙げた①②③、3つの投資スタイルうち、③には特色があります。それは
市場全体の影響を大きく受けない
という点です。
①の場合、本質的価値が高い銘柄でも、市場全体が大幅に落ち込む時期には、大きな影響を受け一時的に暴落する可能性があります。
②の場合も同様に、割安と判断した銘柄でも、市場全体が大幅に落ち込む時期には値下がりしやすく、割高と判断した銘柄でも、市場全体が暴騰する時期には値上がりしやすい。
市場全体のある意味理不尽な動きに引っ張られて、「自分なりの価値と価格のズレの判断」以外の要因で投資成績が左右されてしまいやすい。
その点、③は
●市場全体が暴騰する時期⇒売りポジションの損失を、買いポジションの大幅な上昇でフォローできる可能性
●市場全体が暴落する時期⇒買いポジションの損失を、売りポジションの大幅な下落でフォローできる可能性
が比較的高く、比較的市場全体の大幅な値動きを受けにくい投資スタイルであると思われます。
これは銘柄ごとの割安・割高の判断をある程度正しくできる場合、いつでも投資チャンスが転がっていることを意味し、
株価が上がらない時期でも収益を上げる道はある、かも
と主張する根拠にはなります。
このスタイルの損益は投資家の
銘柄ごとの割安・割高の判断
に大きく依存します。
血眼になって「値下がりしそうな銘柄」を探す
一般的に投資を始めれば
●値上がりしそうな銘柄
●ベターな投資タイミング
を血眼になって探すという体験をすることも多いと思われますが、ロングショートでは投資タイミングを気にせず、
●値上がりしそうな銘柄(買いポジション、ロングの候補)
を探すのと同じくらいの情熱で
●値下がりしそうな銘柄(売りポジション、ショートの候補)
を探索することになります。
優秀なショートポジションが組めれば、少々ロングが失敗しても、ロングショートのトータルで利益を出せる可能性がぐんと上がります。
一般的には最弱の銘柄が、最強の銘柄になることもある、というのがショートの面白さです。
※ロングショートは必ずしもうまくいくわけでもなく、この手法を勧誘するための記事でもありません。投資は自己責任で
※次回に続きます
関連記事