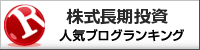為替レートの水準を推し量る一つの視点「実質実効為替レート」で円の水準を観察。
実質実効為替レートを確認するメリット
名目レートだけでなく「インフレ変動」や「貿易額」で調整を施した為替レート(=実質実効為替レート)も知っておくことで、現在の為替レートの水準を知る手掛かりになる、かも
実質実効為替レートとは
2023.5.26現在「1ドル=140円程度」の円のレートは「名目レート」。
実質実効為替レートの「実質」は
「実質」→「インフレ変動(物価変動)で調整した」
の意味。
また、実質実効為替レートの
「実効」→「貿易額などに応じて加重平均して算出した」
の意味。
実質実効為替レートは単純な名目レートではなく、
各国のインフレ変動や貿易額に応じた調整を施した為替レート
のことで、一般的な名目レートでは把握しにくい
通貨の「実力」を推し量る指標
とする人もいます。
※参照
●コトバンク:実質実効為替レート(ジッシツジッコウカワセレート)とは
●金融情報サイト:実効為替レート
スポンサーリンク
円の実質実効為替レートの推移

※出所:Real Broad Effective Exchange Rate for Japan (RBJPBIS) | FRED | St. Louis Fedより作成
※グラフ期間:1994.1月~2023.4月
1994年以降の推移です。
ぱっとみ長期的に円安傾向。
「円安の限界圏」
上記記事の吉田恒氏によれば、
円の実質実効為替レートは5年移動平均からマイナス20%程度が「円安の限界圏」の可能性あり
とのこと。
今回は上記仮説を参考に円水準を考察。
円の実質実効為替レートと5年移動平均

※出所:Real Broad Effective Exchange Rate for Japan (RBJPBIS) | FRED | St. Louis Fedより作成
※グラフ期間:1994.1月~2023.4月
1994年からの円の実質実効為替レートとその5年移動平均。
ざっくりいえば
☆オレンジ線より青線が上にある時期⇒円高?
☆オレンジ線より青線が下にある時期⇒円安?
とするのが吉田氏の見方。

次に5年移動平均から上下どちらに何%ずれているか、5年移動平均からの乖離率を観察。
円の実質実効為替レート、5年移動平均からの乖離率
 ※出所:Real Broad Effective Exchange Rate for Japan (RBJPBIS) | FRED | St. Louis Fedより作成
※出所:Real Broad Effective Exchange Rate for Japan (RBJPBIS) | FRED | St. Louis Fedより作成
※グラフ期間:1998.12月~2023.4月
これでみると2023年4月は「-15.9%」で円安?。
円安の直近ピークは昨年10月の「-21.3%」。
個人的にはまあまあ肌感覚に合う見方。
「円の実質実効為替レート、5年移動平均からの乖離率」と「ドル円」
最後に
「円の実質実効為替レート、5年移動平均からの乖離率」
と
「ドル円」
の推移を併記。
※グラフが見やすくなるので5年移動平均からの乖離率は±を逆転させて表記
 ※出所:Real Broad Effective Exchange Rate for Japan (RBJPBIS) | FRED | St. Louis Fed、USD JPY 過去データ - Investing.comより作成
※出所:Real Broad Effective Exchange Rate for Japan (RBJPBIS) | FRED | St. Louis Fed、USD JPY 過去データ - Investing.comより作成
※グラフ期間:1998.12月~2023.4月
 この期間で主に4回ほど5年移動平均からの乖離率が「-20%」以上の「円安の限界圏」に達したことがあります(グラフ上では±逆転しているので「20%」以上)。
この期間で主に4回ほど5年移動平均からの乖離率が「-20%」以上の「円安の限界圏」に達したことがあります(グラフ上では±逆転しているので「20%」以上)。
①でのドル円のピークは120円程度、その後80円弱まで円高進行。
③でのドル円のピークは125円程度、その後100円強まで円高進行。
④でのドル円のピークは150円程度、その後、現時点では130円程度円高進行。
「円安の限界圏」仮説を裏付ける経験則。
ただ、
②でのドル円のピークは100~105円程度、その後125円程度まで円安が進行しています。
盲目的に
円の実質実効為替レート、5年移動平均からの乖離率が-20%に達しているからドル売り円買い
ポジションを持つと、中銀金融政策次第でときにはひどい目にあうことも。
おわりに
「円安の限界圏」仮説、興味深い視点だったので自分なりに考察してみました。
個人的には盲目的に信じることはできないが、一つの目安にはなりうる見方、経験則と感じます。
本記事では「5年移動平均からの乖離率」を取り上げていますが、3年、7年、10年だったらどうなるのか、気にはなるので気が向いたらまた記事にする予定。