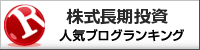米10年債利回りの急騰もあって気になったので
<日米金利差拡大⇒円安> はどこまで正しいか
を検証してみる記事。
「金利差」を決める
<日米金利差拡大⇒円安> はどこまで正しいか
における「金利差」を本記事では
「米10年債利回り-日本10年債利回り=金利差」
とします。
2000年1月~2023年9月の月末値、285個のデータで調査。
「円安」を決める
<日米金利差拡大⇒円安> はどこまで正しいか
における「円安」を本記事では
「円安⇒ドル円の数値が大きくなること」
とします。
2000年1月~2023年9月の月末値、285個のデータで調査。
「米日金利差」と「ドル円」グラフ

※出所:アメリカ 10年 債券 過去データ - Investing.com、日本 10年 債券 過去データ - Investing.com、USD JPY 過去データ - Investing.comより作成
※以下のグラフも同様
青が金利差(%、左軸)、オレンジがドル円(右軸)。
グラフの上に行くほど金利差拡大、円安。
この期間の両者の相関係数は「0.58」。
0.58は「正の相関がある」とされる数値。
因果関係は不明ながら
金利差拡大⇒円安
金利差縮小⇒円高
となりやすい傾向あり。
相関が強い時期

緑で囲ったような時期は相関が強いといえそう。
金利差拡大⇒円安
金利差縮小⇒円高
という傾向が強くみられます。

例えば①の時期。
金利差が「3%⇒1%」に縮小する時期にドル円は「118円⇒90円」に変化。
②の時期。
金利差が「0.5%⇒4%」に拡大する時期にドル円は「110円⇒150円」に変化。
※数値は概算値
相関が弱い時期、逆相関の時期
 緑で囲ったような時期は相関が弱い、あるいは逆相関といえそう。
緑で囲ったような時期は相関が弱い、あるいは逆相関といえそう。
金利差拡大⇒円安
金利差縮小⇒円高
が当てはまりません。
 例えば①の時期。
例えば①の時期。
金利差が「5%⇒2.5%」に縮小する時期にドル円は「110円⇒120円」に変化。
金利差縮小期に円安になっています。
②の時期。
金利差が「1%⇒2.5%」に拡大する時期にドル円は「90円⇒90円」に変化。
金利差拡大期なのに円安に動いていません。
※数値は概算値
まとめ
2000年以降の月末値に関しては金利差とドル円にそこそこの正の相関がありそう。
量的緩和の度合いやインフレ率や景気動向、経常収支など、為替に影響する要因は多そうですが、金利差は比較的説得力のある根拠の一つと思われます。
<日米金利差拡大⇒円安> はどこまで正しいか
はそこそこ正しそう。
※2000年以降の話なので、それ以前のことは不明
それでもいつでも正しいわけでもないので、100%の妄信はやはり危険。
現状に関して、いまだ元気な米景気がもし景気後退となれば、
「米10年債利回り大幅下落⇒金利差縮小⇒円高」
的なことが起こりそうな雰囲気はありますが、先のことは不明。